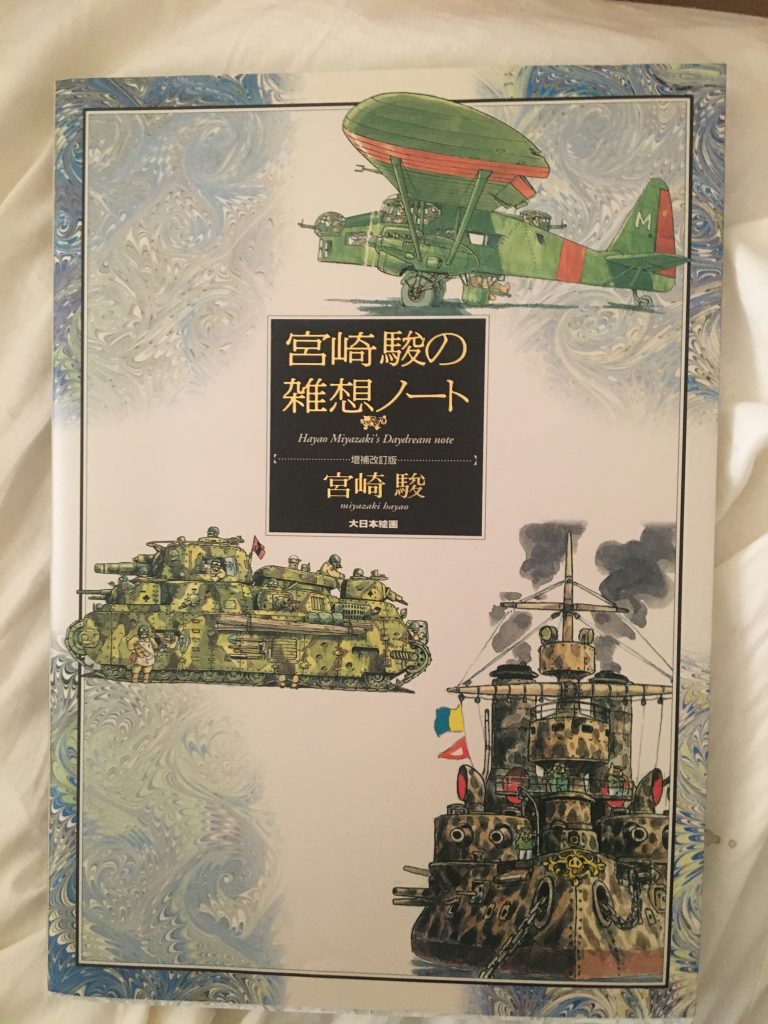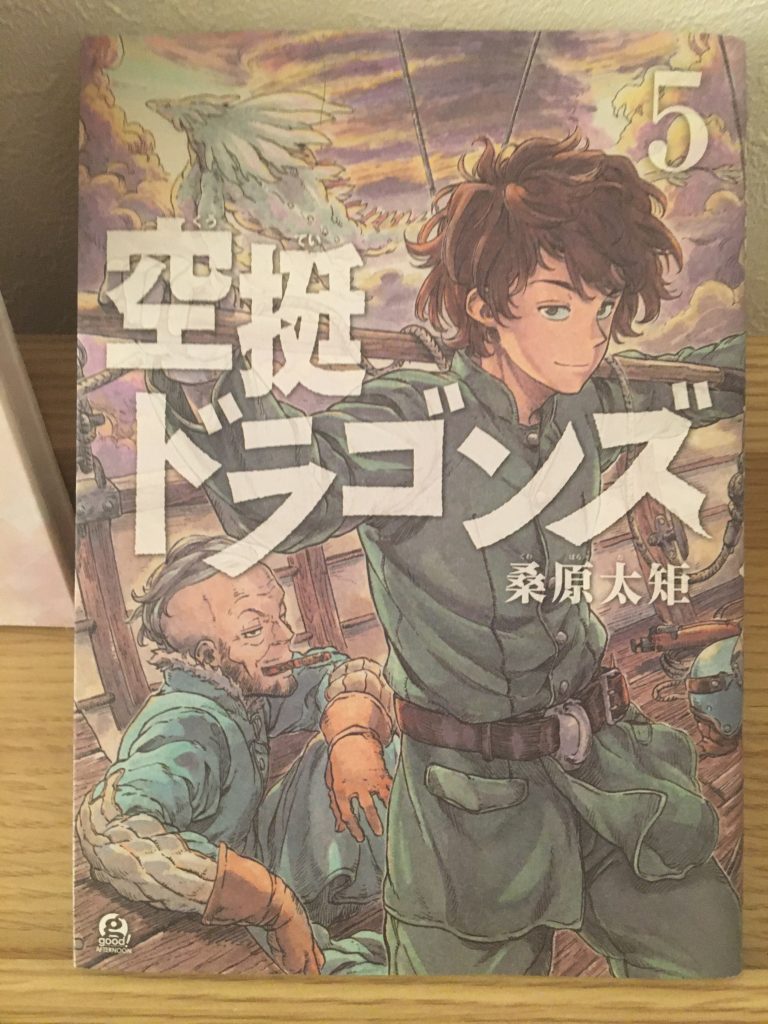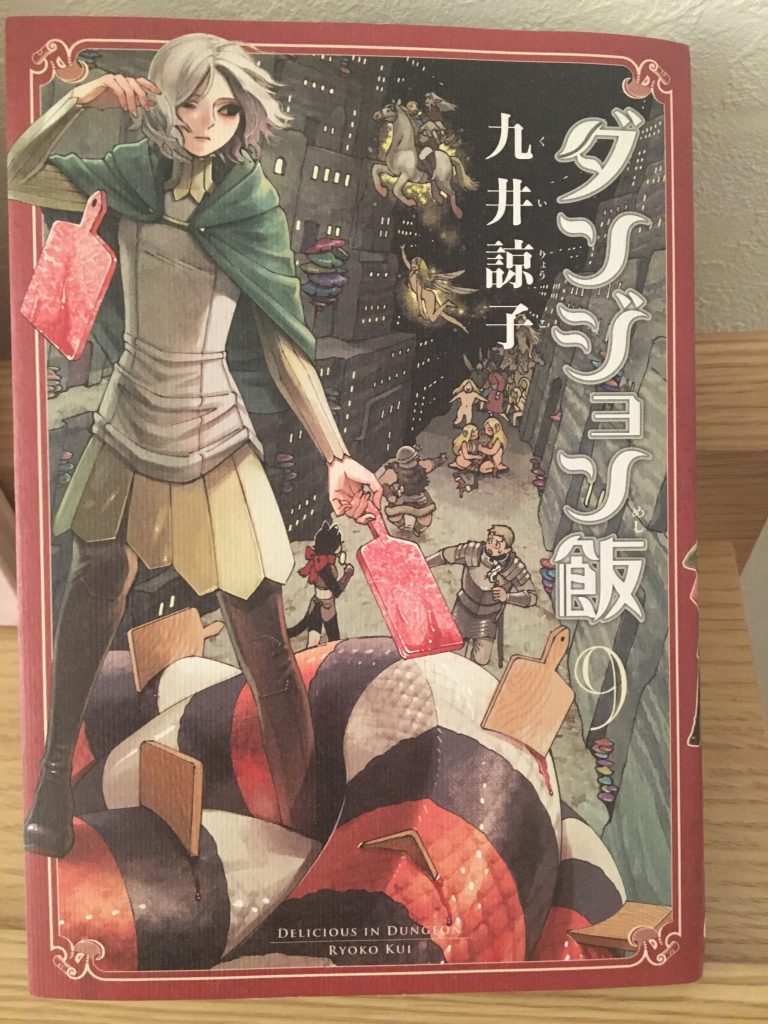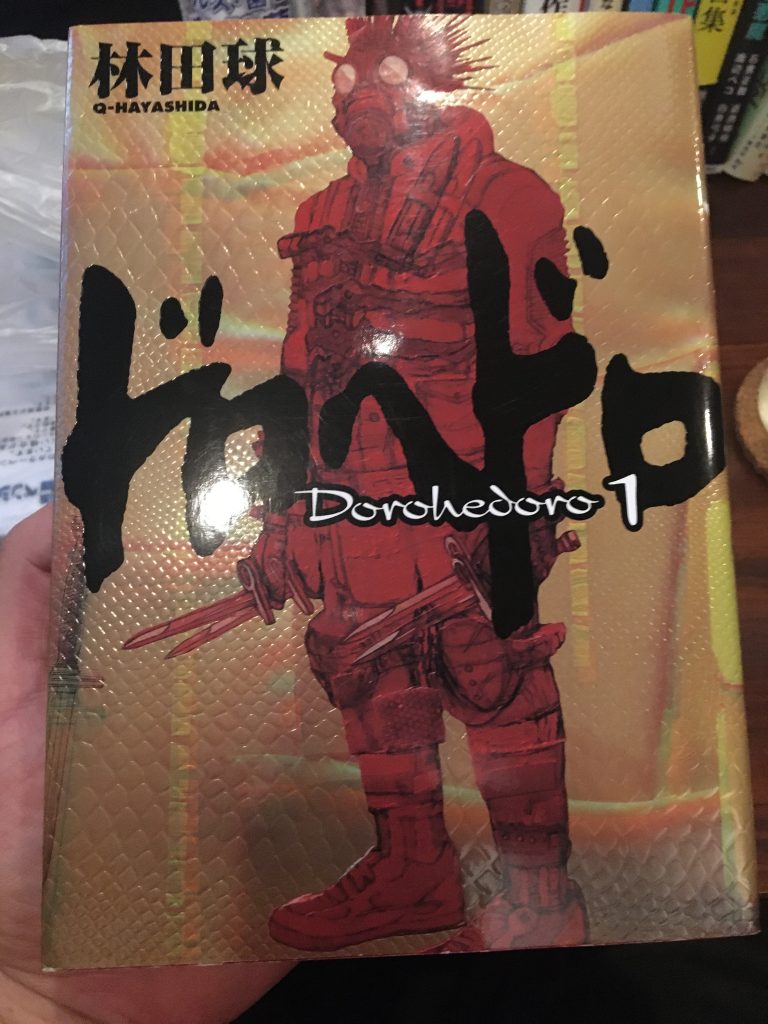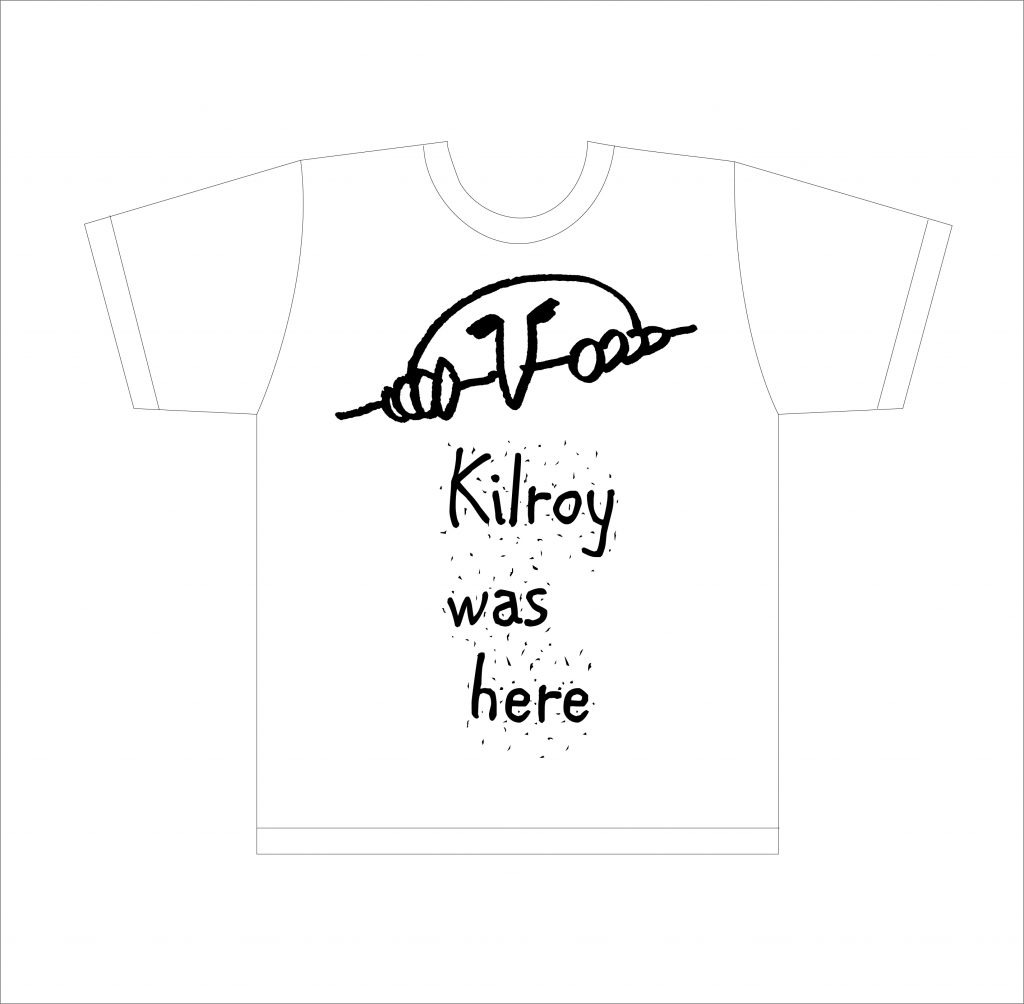ササモトさんとの一件から週末を挟んで派遣現場から離れて、
その間に自分個人の現場を回したり仕込んだりと忙しく過ごし、
五日ぶりに新木場の現場に再度入った。
現場ではまたタケタニさんの下に入る。向こうはすっかりこちらの事を忘れているようで、初心者に教える段取りをもう一度繰り返す。俺はそれを黙って聞き入れて、前回と同じように作業を繰り返す。たったの五日前に会った人間の顔も忘れる、毎日違った傭兵がやってきては消えていく。ここはそういう現場だ。
「じゃあとりあえず午前中はこの椅子磨いといてください、
トラック着たら呼びますから」
「わかりました、雑巾の代えはあそこの棚ですよね」
「え?ああ、そうですけど・・・ああ!こないだ来てましたよね」
雑巾と俺の顔が結びついて記憶を呼び覚ましたようだ。
埃っぽく静まり返る倉庫に一人、安っぽいスチールで出来た折りたたみ椅子を磨き籠車に詰めていく。並べ方が決まっており、それ通りに並べることで最大限積み込むことができる。どんな現場にもノウハウというものが存在するもので、それこそ荷物の上げ下ろしひとつ取っても効率的で安全なやり方というものがある。内装などで使われる石膏ボードなどは一枚の大きさが910×1,820mm程度で重さが12kg程あるが荷揚屋と呼ばれる連中はそれを一度に最低4枚持って階段を昇る。普通に考えると50kg近い重さになるわけだがなにせ平べったく大きく枚数がある、それを狭くて入り組んだ建築途中の現場の中を縫うようにして運び込む。時には一袋20kgのセメント袋3袋の事もある。普通に考えればとてもじゃないがやりきれないが、それをゴリラのようなマッチョが運んでいるかといえばそうとも限らない。体は締まっているはいるが細身の者も少なくない、もちろん基礎的な握力や筋力は必要だが最初の三ヶ月を超えて体が出来上がったら、あとは重心をいかに捉えて重量物を扱うかそのコツを掴むことが肝要なのだ。
そして荷揚屋は一日に数現場こなす事が当たり前で、一現場をさっさと終わらせて次の現場に向かいたい者が多い、必然と一回に持つボードの枚数が増える。超上級者になると6枚程度持つのは当たり前、最後に残った枚数が8枚だろうと10枚だろうと行ってしまう猛者もいるが、そこまでいくと安全が保たれないのでお叱りを受ける事もある。荷揚屋はとにかく脳筋で現場の下支えをする集団ではあるが、同時にプロ意識が高く若衆の格好の修行場となっている。
この倉庫にもスチール製の棚が積み上げてあったので、おそらくあれを整理したりトラックに積み込む作業があるはずだ。俺は椅子を磨きながら心密かにその時を思い担ぎ上げるイメージトレーニングをしていた。そしてトラックがバックで倉庫に入ってくる音が聞こえる。
「すみません、トラックきたんで下に」
俺は雑巾をバケツに投げ入れて階下に向かい、昨日のうちに仕込んでいた籠車を次々にトラックに積み込む。積み込むとはいえトラック後部のリフトゲートに乗せて4~5人で作業を行うので負荷は相当低い。作業強度でいえば荷揚屋の3分の1程度だろうか。そしてうず高く積んであるスチール製の棚を積み込む段になり、俺はその棚に手をかけた。
「ちょっと待て、それはまだやらなくていい」
無愛想で乱暴な物言いをするM社の社員だ。この社員が現場を取り仕切っている男であり、ここ三回ほどの現場入りで観察するにこの男は現場にとっての薬でもあるが毒でもあると思われた。この男の振る舞いは受け流せる者とそうでない者を分けるだろう、物の言い方は乱暴だが間違ってはいない、しかしあまりに相手をねじ伏せる正論であるが故に受け取り手によっては憎しみの感情を呼び覚ます。もしベトナムの戦場にいたら部下に後ろから撃たれるタイプといえばお分かりだろう。
「それは持ち方あるから手を出すな、怪我すんぞ」
「わかりました、あっちの籠車持ってきます」
「わかった、やっとけ」
年の頃は自分よりもまだ若いのだろうが、しかしそれが誰であろうと傭兵に対しては変わらない態度だった。一見して何てことないスチール棚にもその現場の流儀が存在する。乱暴な上官の指示は言葉こそ棘がありぶつけられた物だがその内には新人に怪我をさせない配慮が包まれている。この現場の流れがボチボチと見え始めた。